わたしのオーディオシステム〈その2〉アナログシステム ■ ターンテーブルCEC FR-XA1/トーンアームIKEDA IT-407/シートは5ミリ厚のソフボセインのレーベル面をドーナツ状に切り取ったものの上に鹿皮シート、fo-Qシートを乗せている。IT-407にはレコードに針をのせたまま高さが調節できる、特注アームベースを使用。(2008年現在)
■ ターンテーブルCEC FR-XA1/トーンアームIKEDA IT-407/シートは5ミリ厚のソフボセインのレーベル面をドーナツ状に切り取ったものの上に鹿皮シート、fo-Qシートを乗せている。IT-407にはレコードに針をのせたまま高さが調節できる、特注アームベースを使用。(2008年現在) ■ メインカートリッジは、IKEDA 9 Supremo/My Sonic Lab EMINENT/オルトフォンSPU Meister Silver の本体をシェルから取り出して、サエクの専用ベースを介してカーボン製シェルに取付けたものなど。MC昇圧トランスはIKEDA IT-10のトランスを自作プリアンプ内に組込んである。
■ メインカートリッジは、IKEDA 9 Supremo/My Sonic Lab EMINENT/オルトフォンSPU Meister Silver の本体をシェルから取り出して、サエクの専用ベースを介してカーボン製シェルに取付けたものなど。MC昇圧トランスはIKEDA IT-10のトランスを自作プリアンプ内に組込んである。
「アナログをあなどるとはアナクロな!」
このデジタルオーディオの時代に、いまだに数千枚のアナログレコードを手放せない。いや、手放さないどころか、今も増え続けている。いつかそのうちきちんとセレクト整理して、聴くことのないであろうアルバムは手放すかもしれない。だが、一生アナログは聴き続けると思う。それほどアナログは魅力的だ。
うれしいことに最近、ふたたびアナログが注目されているのだそうだ。新譜アナログレコードも僅かながら発売されている。入門用の1万円たらずのレコードプレーヤーはたくさんあるし、ハイエンドオーディオ向けのアナログ機器は健在だ。アナログで育った団塊世代の大量定年退職のせいもあるだろうが、iPodのイヤフォンをぶら下げた若者の中に、アナログレコードに興味を抱くマイノリティが生まれていることはたしかだ。
30年来たずさわってきた広告業界にも、15年ほど前からデジタルの波は押し寄せた。広告印刷物にかかわる業種は特にひどかった。はじめに写植屋がその波に呑み込まれた。写植とは印刷原稿(版下)に貼り付ける広告コピーを印画紙に叩き出す仕事。印刷広告の入稿原稿制作のためには不可欠な業種だった。発注していた写植屋の現場オペレーターは、ピカピカのまっ赤なポルシェに乗っていた。だがデジタル入稿は、印刷入稿の版下の存在自体を不要にしてしまったのだ。次いで製版業が消えかけている。製版業がやっていた作業は今、デザイナーがそのほとんどを担っている。パソコン画面上で。
ほかにも広告制作にかかわる業種のほとんどが、何らかのデジタルの洗礼を受けている。私が生業としているアートディレクションの立場でも同様だが、利点もあった。デジタルのおかげで企画から制作、印刷入稿までの一切をアートディレクター自らがコントロールできるようになった。作業のすべてに自分の想いを込められるのだ。アートディレクターの100%アナログな感性を、デジタルによってさらに生かせるということだ。
アナログな感性をデジタルの作業性で豊かなものにできる。アナログとデジタルの共栄。いや、デジタル(手法)は人間のアナログな創意のためにあってこそ、デジタル本来の役割が果たせたといえるはす。未だにネットサーフィンもおぼつかないというのでは、せっかくのデジタルを活かしたことにはならないが、一方で携帯電話に依存したり、ネットの誘惑に負けたりということでは、デジタルの負の部分しか味わったことにならない。最悪だ。
エクスタシーオーディオのコラム「アクセサリーエクスタシー〈2〉」で、アナログ音源をデジタル変換して、再度アナログに戻す(リマスターする)ことで音質を向上させるアクセサリー機器を紹介している。デジタルの機能がアナログな感性をとり戻し豊かなものにしたのだ。どちらかがどちらかを否定したり拒絶するのではない。人間というアナログの可能性をデジタルという手法によってさらなる高みへと昇華させること。デジタルの価値は、アナログのためのものだということを忘れてはならない。
![]() プロフィール&システム
プロフィール&システム
 HOME
HOME

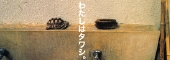





 前のページへ
前のページへ