Secret Knowledge.
2008.8.29
名探偵ホックニー
8月17日まで東京国立博物館で開催していた「対決ー巨匠たちの日本美術」を観た。企画の立て方は興味深いものだったが、いかんせん「頭で美術を鑑賞する」典型な展覧会だった。
旭山動物園の劇的な再生の成功以降、いろいろなアミューズメント施設が「企画」で客を呼ぼうと努力しているが、文化施設である博物館や美術館までがその流れにまきこまれているらしい。
最終日の前日の午後、強い雨が降る中、いつものように鴬谷から博物館に向かったのだが、大雨だというのに45分待ちで、ずらりと長い列が平成館の左手にグレーに霞んで見えた。展覧会としては大成功ということなのだろう。
名品の屏風などの大作が多くそれなりに見応えはあったが、多くの観客が皆ショーケースに張り付いているために、せっかくの大作がちゃんと見えない。「大きな作品をそんなに近くで観ちゃいけないよ」心の中でつぶやきながら、あきらめて頭越しに鑑賞することにした。
途中でおもしろい現象をみつけた。長沢芦雪の虎図襖や長谷川等伯の松林図屏風など、数点の水墨画の名品の前に人だかりがほとんどないのだ。おかげで芦雪の虎図など、じっくりと鑑賞することができた。手塚治虫のロボットみたいな虎のギョロ目、大好きすばらしい。
ほとんどの観客は絵の細部だけをみて感動しているようなのだ。ガラスに張り付いて。絵を描く素養がないからといってしまえばそれまでだが、勢いのある筆致で一気に描き上げていくことの凄さは、水墨で描くことの難しさを知っている人間にしか分からない。細密な絵画は「努力」でそれなりに描けるものだが、やり直し塗り直しのきかない墨絵であれだけの完成度を上げるためには、才能というか才気のようなものを身につけてなけりゃ、けっして描けるものではない。
私も芸大をめざして一念発起、公務員を退職して美術予備校へ通った経験がある。一年間でずいぶんデッサン力はついたが、中世西洋絵画のような、スーパーリアルな絵はとても描けるものじゃない。世の中にはすごい画力を持った天才がいるものだと、自分の才能の小ささを嘆いたものだ。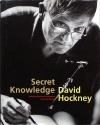 ところが、そんなスーパーリアルな絵画には何かカラクリがあるはず、と仮説を立てて研究したアーティストがいるのだ。デービット・ホックニー。ポラロド写真をコラージュした一連の作品などでよく知られる、現代アートの重鎮のひとりだ。そのホックニーの研究成果を一冊の書籍にまとめたのが「Secret Knowlege David Hockney 秘密の知識 巨匠も用いた知られざる技術の解明
ところが、そんなスーパーリアルな絵画には何かカラクリがあるはず、と仮説を立てて研究したアーティストがいるのだ。デービット・ホックニー。ポラロド写真をコラージュした一連の作品などでよく知られる、現代アートの重鎮のひとりだ。そのホックニーの研究成果を一冊の書籍にまとめたのが「Secret Knowlege David Hockney 秘密の知識 巨匠も用いた知られざる技術の解明」だ。(画像クリックで拡大表示)
よくある美術書サイズの大型本で、分厚くとっつきがわるい体裁だが、内容はほとんどが名画の図版である。
ここでちょっと話がそれる。
子供の頃、よく実家二階の北側の部屋にこもってひとり遊んでいた。雨戸を閉めた六畳の畳の部屋は湿っぽく薄暗くて、子供一人では怖かったはずなのだが、ちっともそんな気持ちにはならなかったみたいだ。雨戸の内側はスリガラスの嵌った膝下まであるガラス戸がついていて、何カ所かの雨戸の節穴からもれる外光が、ぼんやりとスリガラスを照らしていた。いくつかの背の届く、その丸く照らされたガラス戸に目を近づけると、ぼーっと色のついた絵のようなものが浮かんでいる。節穴の大きさはいろいろで、大きすぎるのはぼんやりしているが、ちょうどいい大きさのはかなりくっきりと絵が見える。天地(左右だったか?)が逆さまになった家の裏の風景だ。すぐ裏の屋根も樹々も、ときには屋根の上をはばたく鳥の動く姿まで幻灯のように見ることができるのだ。雨戸の節穴がレンズの役割を果たして、近所の景色をスリガラスの上に定着させているというわけだ。
さて、ホックニーにもどろう。ホックニーの仮説、それは「中世絵画の多くはカメラの技術を用いていたのではないか」というものだ。もちろんカメラとしての印画紙への定着技術が開発されるのは近世になってからであるから、ここでいうカメラの技術とは、私が子供の頃絵心をふくらませたのと同じ原理で、レンズを使って実画像を写し取るという、絵画への応用のことだ。
ホックニーの調査によると、宗教画にしろ肖像画にしろ中世のある時期から、なぜかとてもリアルな超絶的な技巧による絵画が現れてくる。「Secret Knowlege」の前半では、数多くの名画でその変化を説明している。その時期とレンズの発達とが時代的にリンクしているというのだ。仮説のきっかけは、ロンドンのナショナルギャラリーでアングルの肖像画展を見たとき、その素描のすべてがとても小さく描かれていること、おそろしく正確に描かれていること、しかもそのタッチに迷いがまったくなかったことなのだそうだ。 カメラ・オブスクーラとかカメラ・ルシーダという名前の光学装置が登場してくる。ホックニー自身カメラ・ルシーダを用いて多くの肖像や静物を描いてみたりして、その使用の難しさや可能性を実体験している。
カメラ・オブスクーラとかカメラ・ルシーダという名前の光学装置が登場してくる。ホックニー自身カメラ・ルシーダを用いて多くの肖像や静物を描いてみたりして、その使用の難しさや可能性を実体験している。
左の図版はデューラーが1525年に制作した木版画で、レンズすら使わない簡素な道具で二人がかりでリュートの形を再現している。カメラ・ルシーダとは棒の先につけたプリズムがその前にある物の像を下の紙に映し出す仕掛けだという。 あまり種明かしをするのは下品なのだが、光学機器を用いて描かれた絵画には大きく二つの特徴があるという。一つ目は光学機器を使ってトレースできる範囲は限られているため、大きな画面を構成するためには、トレースした下絵を繋げなくてはならず、そのために一枚の絵の中にいくつものパースの消失点ができてしまう。そのことを多くの名画のなかに見つけ出している。もう一つは左のフェルメールの有名な作品に見られるように、肉眼では見ることができない、レンズ越しににしか見えない光のフレア(光学効果)が描かれているという点だ。(テーブルに置かれたパンや壺、壁に掛けたカゴなどの空間への反射光)
あまり種明かしをするのは下品なのだが、光学機器を用いて描かれた絵画には大きく二つの特徴があるという。一つ目は光学機器を使ってトレースできる範囲は限られているため、大きな画面を構成するためには、トレースした下絵を繋げなくてはならず、そのために一枚の絵の中にいくつものパースの消失点ができてしまう。そのことを多くの名画のなかに見つけ出している。もう一つは左のフェルメールの有名な作品に見られるように、肉眼では見ることができない、レンズ越しににしか見えない光のフレア(光学効果)が描かれているという点だ。(テーブルに置かれたパンや壺、壁に掛けたカゴなどの空間への反射光) このフェルメールの解説ページに面白い記述がある。(一部転載)
このフェルメールの解説ページに面白い記述がある。(一部転載)
『この召使いはフェルメールが描いた人物のなかで、最も存在感があることを指摘しておきたい。フェルメールの絵によく登場する上流夫人たちよりも、ずっと手応えがある。それはこの女性が召使いであり、上流夫人であれば「頭痛がしますわ、ちょっと横にならせてくださいね」などと言って中断するところを、じっと我慢してくれたからであろうか。』
レンズを使ってトレースするのは画面が小さく難しく、モデルが少しでも動くとうまくトレースができないためだ。左のページは、ホックニーが実際に光学機器を使ってモデルをトレースしているところだ。
もちろん、すぐれた画才がなければ、いくらモデルを正確にトレースしたところで、それを絵画に仕上げることができないのはいうまでもない。
アングルの素描とアンディ・ウォーホールの素描の比較からはじまって、パースの矛盾やモデルの表情の変遷など、数多くの名画を引用し比較して、次第に核心にせまっていく展開は、まるで巧妙な推理小説でも読んでいるようにスリリングでおもしろい。
昔の名のある人々だって、きっと自分の肖像をリアルに残したかったはずだ。写真みたいに。もちろんそこには自身の威厳や美化への希求も含まれる。Photoshopでレタッチするみたいに。ライカで撮るかニコンで撮るかという感じで、いや、カメラマンを選ぶような感じで、カラヴァッジョに描かせようかベラスケスにしようか、とか言ってたりしていたのかもしれない。
 HOME
HOME





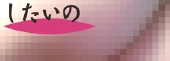

 前のページへ
前のページへ